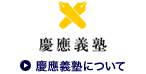2023年度公募プログラム
[法務研究科]
グローバル法務人材の育成
活動代表者
法務研究科委員長 北居功
慶應義塾大学大学院法務研究科は、その設立当初より国際化を標榜してきたが、未来先導基金の活用を通じて海外の大学や機関で経験と研鑽を積んだ法務研究科学生が、将来、国際分野で活躍することを大いに期待している。
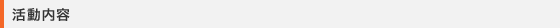

ラオス人民民主共和国を訪問し,日本および国際機関による法整備支援の最前線の活動に触れた。
まず,ラオス人弁護士の法律事務所を訪問し,業務の内容,日本を含む外国企業の案件,国内の案件,弁護士会の活動等について解説を受け,ラオス社会において弁護士の役割が徐々に認知され,その活動の範囲が徐々に拡大してきていることを知ることができた。
ついで,国際協力機構(JICA)のラオス法整備支援プロジェクト・オフィスにおける専門家の講義を受け,現在のプロジェクト内容,従来のプロジェクトとの関係,JICAによる法整備支援の特色について,ディスカッションした。その際には,専門家が現在抱えている課題についても共有することができた。
さらに,ラオス法整備支援プロジェクトの一環としての,民法および刑法における法の解釈に関する現地セミナー(2024年2月6日~8日)に参加し,憲法上,法の解釈権限が国会の常務委員会に付与されている中で,裁判官,検察官,弁護士等の法曹,司法省の公務員等の行政官が,個々の事案の処理において,実務上法の解釈をどのように扱うべきか,比較法的にみて,法の解釈の方法にはどのようなものがあるかについて,一般的な方法論の検討と,民事・刑事の各分野での個別問題を通じての検討について,議論を聴講し,法学教育および法曹教育の在り方について考察した。
その後,ラオス国立司法研修所(NIJ)において,ラオスにおける法曹養成制度について説明を受け,その現状について質疑・応答を行い,その教材づくりや授業方法について,日本がどのように協力できるかについて考える機会を得た。
最後に,国連開発計画(UNDP)ラオス事務所を訪問し,法の支配およびガバナンスに関するプロジェクトのチームリーダーおよびメンバーから,法の支配および良い統治を構築することを目標とするラオスにおける活動についても解説を受け,今後の課題について議論を行った。
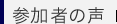
公募プログラム
法務研究科3年
今回のエクスターンシップは法律学の学習と自身のキャリアに関してとても有益でした。前者については、そもそも自分達が当たり前と思っていることであっても、違う国では当たり前でなかったり、国家体制によって独自の論点があったりと、法律学は普遍的な部分もあれば国や地域ごとに特有のものもあるということを学べそこに面白さもあると感じました。また自分の当たり前を前提として他人に話すことは価値の押し付けになりうる危険があることも知ることが出来ました。後者については、将来 JICA の専門家の方々のように法整備支援に携わるかはわからないものの、一つのキャリアとして専門家の方から直接業務のやりがいを聞くことができたことは大きかったと思います。今のところ弁護士事務所に入って企業法務をやりたいと考えていますが、事務所内でも東南アジアの現地オフィスでの法整備支援プロジェクトがあり、JICA のような機関に就職し携わるかは別として、何らかの形で携わりたいと思いました。それくらい専門家の方々のやりがいを聞いたり、現地の方々との交流の様子を見たり、着々と法が浸透してきたりしている様子をみて魅力的な業務と感じました。また他国の文化や風習を尊重する姿勢は、法整備支援だけでなく、海外取引がある業務全般について共通するものだと思うので、その重要性を認識できたことは大変良かったです。
このエクスターンシップへの参加は昨年度から興味がありましたが、まだ司法試験受験前という状態かつ久しく海外に行っていなかった私にとっては、なかなか参加しようと決断することができませんでした(言い訳かもしれませんが)。しかしせっかくローに入学したのだから、やれる機会を逃してはいけないとの思いで思い切って参加を決め本当に良かったです。今回現地の人々、日本人の専門家の人々などたくさんの方々にお会いして、法曹としてのキャリアについて改めて考えさせられる機会となりました。参加者の方とも毎日自分達の将来について真剣に考え、知識面だけでなく価値観や視野といった面でも自分の幅が広がったように思います。松尾先生がいらっしゃるこの慶應ローならではのこのエクスターンシップが今後とも続いていけば本当にいいなと思っております。ありがとうございました。
法務研究科3年
特に勉強になったこととしては、やはり国ごとに国体は異なることから、法律の社会でのあり方や、使われ方は全く異なるということです。解釈を当たり前にしてきた自分の考え方はあくまで日本などの一定の国の考え方でもあるという風に気づけました。
また、現地のセミナーにおいて、現地の専門家や村の方など、多くの方が積極的に参加していたことが印象的でした。セミナーの内容それ自体がセンセーショナルであったことに加え、日本の専門家を目の前にして法律を学ぶ姿勢に感銘を受けました。
法律学の学習という点においては、法解釈学の原点に立ち返ることができたと思いました。ラオスは社会主義国であり、法律の解釈権限は常務委員会という国会の権能とすることが憲法上定められています。したがって、法律の解釈、その上での事実への当てはめという概念がいまだに浸透しているとは言えない状況の中で、現地の文化や社会に反しない、また、主権を侵さない範囲での解釈の可能性を見つけていく一つの過程を見ることができ、勉強になりました。