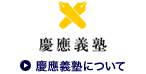2025年度公募プログラム
[協生環境推進室]
協生環境×情報アクセシビリティ:誰もが学べる読書とWEBのキャンパスづくり
活動代表者
経済学部教授/協生環境推進室バリアフリー推進事業委員会委員長 中野泰志
 読書とWebのバリアフリー化を通じて、すべての人に開かれた学びの場を実現します。
読書とWebのバリアフリー化を通じて、すべての人に開かれた学びの場を実現します。
本ACCESS+プロジェクトでは、情報にアクセシビリティというプラスの価値を付加することで、慶應義塾のすべての構成員が情報にアクセスできる環境を整備することを目的とする。学部生・大学院生に広く参加を呼びかけ、障害のある当事者および専門家と連携して実践的な情報アクセシビリティを推進しつつ、アクセシビリティの理念を体験的・共感的に理解する。参加学生は読書アクセシビリティユニット(RAX)とWEBアクセシビリティユニット(WAX)に分かれ、それぞれの専門分野においてワークショップやフィールドワークを通じた課題解決型の実践を行う。
(1)事前研修【アクセシビリティの理念の理解】
プログラムの導入段階として、障害をめぐる現代的な理解に基づき、国連「障害者権利条約」に示される社会モデル・人権モデルの視点を学ぶために障害当事者が推進する障害平等研修(Disability Equality Training:DET)に参加する。また、障害当事者とのディスカッションを通じて、情報アクセシビリティの理念を体験的・共感的に理解する。
(2)実施準備【調査と実践に向けた基礎学習】
各ユニットは、担当分野における調査・実践の基礎的知識を習得する。
①RAXは、視覚障害者等の読書環境の現状を理解し、資料のテキストデータ化・音声化の手法、ならびにアクセシブルな閲覧アプリ開発における技術的・倫理的配慮を学ぶ。
②WAXは、アクセシビリティの国際的ガイドライン(WCAG)や支援技術(スクリーンリーダー等)の使用法、実際のWebサイト評価手法について学習する。
(3)ワークショップ【読書・Webアクセシビリティ向上の実践】
①RAX:慶應義塾大学図書館の蔵書を対象に、アクセシブルな形式(テキストデータ化・音声化等)への変換作業を体験的に学ぶワークショップを実施する。変換後の資料を国立国会図書館の「みなサーチ」に登録する手続きについても学び、障害学生の読書環境整備に寄与する。また、閲覧用アプリの開発・改良の事例をもとに、PDCAサイクルに基づく設計・評価・改善プロセスを体験的に理解する。
②WAX:学内の公式Webサイトを対象にを行い、障害のある当事者とともにアクセシビリティチェックをする。評価結果に基づき、JIS規格やWCAGに準拠した改善案を考案し、よりアクセシブルなWebサイトのあり方について提案するワークショップを行う。
(4)成果の発信【報告会の開催】
各ユニットは、活動を通じて得た知見と提案を取りまとめ、「2025年度 協生環境推進ウィーク」において活動報告セッションを開催し、学内外に向けて成果と課題意識を発信する。なお、提案をまとめた報告は、大学の関連部門(図書館、広報室、ITセンター等)に提出し、具体的な改善につなげる。