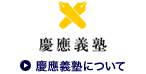2024年度公募プログラム
[福澤研究センター]
福澤諭吉と近世の街を「体験」するワークショップ ― 城下町豊前中津の空間と学問、産業 ―
活動代表者
福澤研究センター所長 平野隆
 このプログラムは、高校生から大学院生までを対象に、福澤諭吉の郷里中津を徹底的に深めます。中津は空襲が無かったため、近世の城下町の区画がよく保存されており、福澤諭吉の『福翁自伝』の世界をたどることが出来ます。福澤の若き日を追体験しながらその思索をたどることは、現在の慶應義塾を考え、皆さん自身の未来を考えることにつながるでしょう。
このプログラムは、高校生から大学院生までを対象に、福澤諭吉の郷里中津を徹底的に深めます。中津は空襲が無かったため、近世の城下町の区画がよく保存されており、福澤諭吉の『福翁自伝』の世界をたどることが出来ます。福澤の若き日を追体験しながらその思索をたどることは、現在の慶應義塾を考え、皆さん自身の未来を考えることにつながるでしょう。

・未来先導基金の追加募集での採用となったが、高大交流ができる適切な期間は夏休みしかなく、早急に計画準備を行い、8/29(木)~31(土)の2泊3日と決定、7月中に公募、抽選し23名の参加者を決め、8月の事前説明会で、『福翁自伝』や『学問のすゝめ』を事前学習するなどの説明を行なった。
・8/29(木)折からの台風10号の九州直撃を受け、現地の交通網が休止・寸断され、本人や保護者の不安、また現実的にも現地に到着できても行動がまったくできない状況のため中止を余儀なくされた。
・8/29(木)は、東京への台風接近前でそれほど影響がないことが見込まれたため、三田キャンパス南校舎466番教室を確保し、急遽代替企画を計画して、参加予定者へ希望を募った。23名中14名が参加し、引率予定の教員4名も全員参加して実施した。
・代替行事の内容としては、①中津の街から福澤を深める+街歩き疑似体験・グループワーク(担当:山内慶太)、②中津の町を他の城下町と比較してみよう・グループワーク(担当:池田卓也)、③三田演説館見学(解説:都倉武之)、④慶應義塾史展示館企画展特別ギャラリートーク(解説:都倉武之)、⑤茶話会を行った。
・当初参加予定だった塾生の2/3程度の参加であったが、普段掘り下げることができない側面から意見を出し合いながら考える、密度の濃い有意義な時間となった。また、短い時間ではあったが、高校生と大学生が一緒に考え、活発に意見を出し合う場が生まれ、改めてこの機会を設ける意義が再認識された。
「福澤諭吉と近世の街を「体験」する旅 — 城下町中津で学ぶ2泊3日 — (福澤研究センター主催 慶應義塾未来先導基⾦プログラム)
https://www.fmc.keio.ac.jp/news/3039
今回は、本プログラムは中止となった形のため、アンケート等で意見聴取を行わなかった。連絡に添えられたコメントが若干あったため、それを参考までに以下に記載する。